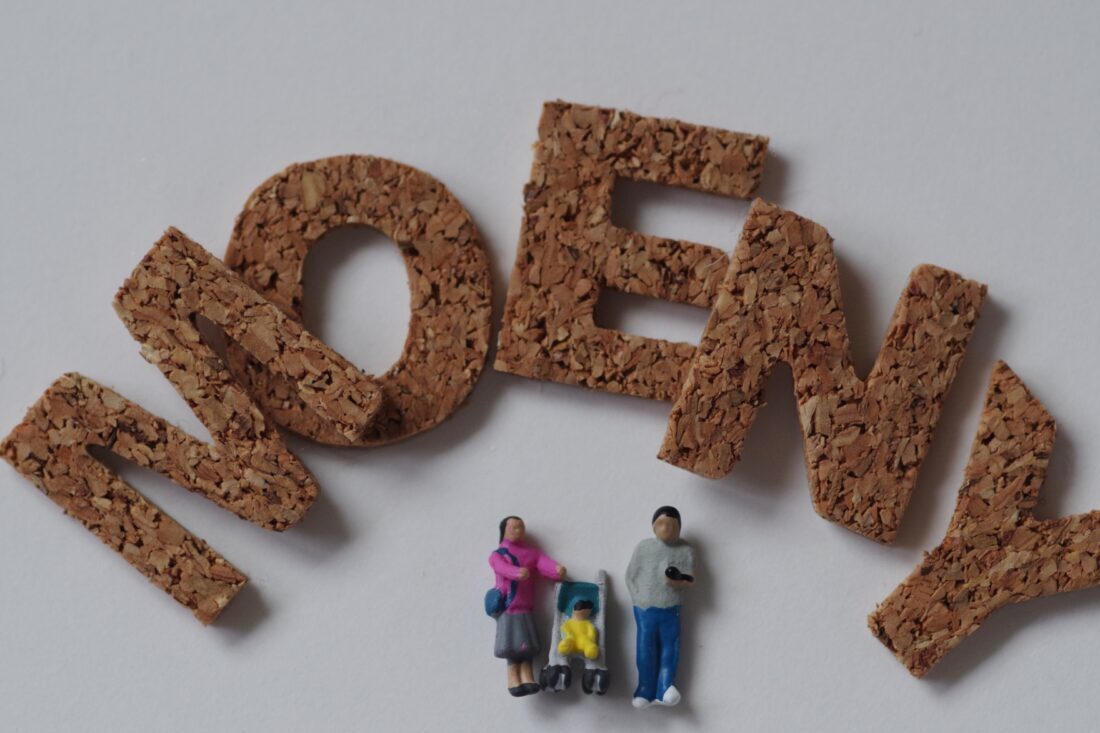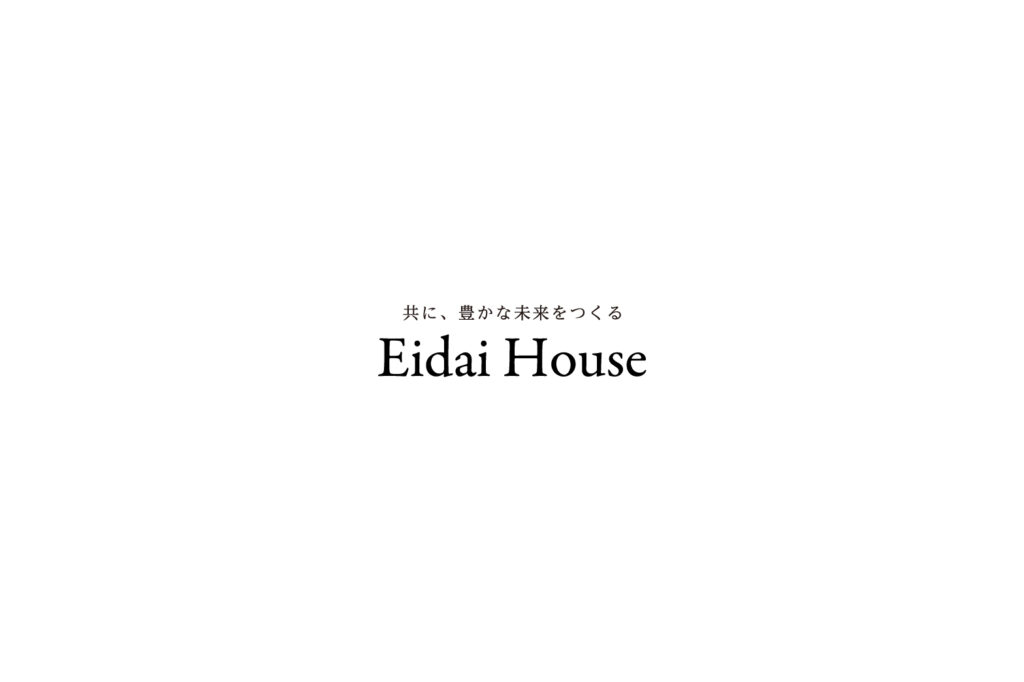目次
1. 「いくら借りられるか?」よりも「いくらなら、暮らしを楽しめるか?」
住宅ローンを考えるとき、多くの方が気にするのは「自分はいくら借りられるのか?」という点です。銀行の審査を通れば、数千万円という大きな金額を借りることも可能です。しかし実際の生活で本当に大事なのは、「借りられる額」ではなく「安心して返せる額」です。
毎月の返済額がわずかに違うだけで、暮らしの余裕度は大きく変わります。たとえば返済が10万円なら少し無理を感じる家庭でも、8万円なら旅行や外食の楽しみを残せるかもしれません。福岡でいえば、糸島の海辺でランチをしたり、子供たちの教育や体験に費用をまわしたり。そうした日常の小さな楽しみや、将来への投資は、返済額とのバランス次第で続けられるかどうかが決まります。
2. 借入額別シミュレーション(35年返済・元利均等・ボーナス払いなし)

ここでは「金利1.0%」「金利1.5%」の2パターンで、借入額3,000万・4,000万・5,000万円の月々返済額をシミュレーションしました。
| 借入額 | 金利 | 月々返済額 | 総返済額 |
| 3,000万円 | 年1.0% | 約84,686円 | 約3,557万円 |
| 3,000万円 | 年1.5% | 約91,855円 | 約3,858万円 |
| 4,000万円 | 年1.0% | 約112,914円 | 約4,742万円 |
| 4,000万円 | 年1.5% | 約122,474円 | 約5,144万円 |
| 5,000万円 | 年1.0% | 約141,143円 | 約5,928万円 |
| 5,000万円 | 年1.5% | 約153,092円 | 約6,429万円 |
毎月の返済額だけ見ると「少しの差」に見えますが、35年続けば総額で数百万円の差となります。これは無視できません。
3. 住宅ローンの返済方式 ― 元利均等返済と元金均等返済
返済額を計算するときに大切なのが「返済方式」です。
- 元利均等返済
元金と利息を合わせた返済額が毎月ほぼ一定。家計管理がしやすく、初めて住宅ローンを組む人に選ばれることが多い方式です。ただし、最初のうちは利息の割合が多く、元金がなかなか減りません。 - 元金均等返済
毎月返す元金部分は一定で、利息分が徐々に減るため返済総額は少なくて済みます。ただし最初の数年は返済額が高くなるので、家計に余裕のある世帯向きです。
返済方式の比較例
仮に3,000万円を35年で借りた場合、金利1.0%では元利均等なら月々約8.4万円ですが、元金均等では初期に約9.6万円となり、その後少しずつ減っていきます。総返済額は元金均等のほうが少なく済む一方、初期負担は大きくなります。この差を理解して選ぶことが重要です。
4. 金利タイプの違い ― 変動金利と固定金利、そしてフラット35
住宅ローンの返済額は金利次第で大きく変わります。
- 変動金利
半年ごとに見直され、金利が下がれば返済額も減ります。現在は低金利が続いているため人気ですが、将来上がったときには返済額が膨らむリスクがあります。実際に1990年代には金利が5%を超えた時期もあり、その頃に借りた世帯は大きな負担を抱えました。もし現在1.0%で借りていたローンが2.0%に上がったとすると、3,000万円借入で月々約8.4万円→約9.9万円へと1.5万円増え、年間では18万円、35年で600万円以上の差となります。 - 固定金利
返済中ずっと金利が変わらない安心感があります。金利は変動型より高めですが、長期的な計画を立てやすいのがメリットです。教育費や老後資金の見通しを立てたい家庭には向いています。
2025年8月時点では、変動金利が0.525%前後、固定金利(フラット35)は1.870%程度と差があります。 - フラット35
国が支援する固定金利型ローン。最長35年間、返済額が一定です。利用には住宅の床面積や技術基準を満たす必要がありますが、省エネ性能や耐震性能が高い住宅を建てれば金利優遇が受けられます。団体信用生命保険(団信)も付帯でき、病気や死亡時のリスクにも備えられる安心感があります。中古住宅でも利用できるため、リノベーションを考えている方にも活用されています。
5. 家計シミュレーション ― 世帯年収別のリアルな暮らし
年収500万円(子育て世帯)
借入額3,000万円、金利1.0%、返済期間35年の場合、月々の返済額は約8.5万円。手取り月収はおよそ33万円となり、ローンを差し引くと残りは24.5万円です。
この中から生活費(食費・光熱費・通信費など)に15万円、車の維持費に3万円、子どもの教育費に3万円を充てると、貯蓄に回せるのは約3万円。余裕は限られますが、堅実な家計管理を心がければ、無理なく返済を続けることが可能です。
ただし、教育費は中学・高校・大学と進学するにつれて増加するため、早期の備えが重要です。特に私立大学まで進学する場合、総額1,000万円を超えるケースもあり、住宅ローンと並行して教育資金を計画的に準備する必要があります。
年収700万円(共働き世帯)
借入額4,000万円、金利1.0%、35年返済で、月々の返済額は約11.3万円。手取り月収は約46万円となり、ローンを支払った後も34.7万円が残ります。
生活費に15万円、教育費に5万円、車2台分の維持費に6万円を充てても、約8万円が貯蓄やレジャーに回せる計算です。福岡市のような都市であれば、週末に糸島や柳川へ出かけたり、家族で外食を楽しむ余裕も生まれます。安定した生活を送りながら、老後資金の積み立ても無理なく始められる水準です。
よく話題に上がる「老後2,000万円問題」に対しても、この収入帯であれば現実的な備えが可能です。
年収1,000万円(ゆとりある世帯)
借入額5,000万円、金利1.0%、35年返済で、月々の返済額は約14.1万円。手取り月収は約65万円となり、返済後も50万円が手元に残ります。
生活費や教育費を差し引いても十分な余裕があり、老後資金の積み立てはもちろん、投資やセカンドハウスの検討も視野に入ります。生活水準を高めながらも、無理なく返済できる典型的なモデルケースといえるでしょう。
6. 福岡の住宅市場の特徴と返済計画
福岡市は全国的に見ても人口増加が続く数少ない都市で、住宅需要も高まっています。中心部の博多区・中央区は土地価格が高めですが、東区香椎や西区姪浜、城南区などは比較的手ごろで、子育て世帯に人気です。さらに郊外の新宮町や春日市、大野城市は交通アクセスが良く、土地価格も抑えられるため、ローン負担を軽減しながらゆとりある住まいを実現できます。
また、福岡は車社会でもあり、1世帯あたりの車保有率が高い地域です。車の維持費が年間数十万円かかることを考えると、首都圏に比べて住宅価格は抑えられていても、生活コスト全体でみると慎重な返済計画が求められます。一方で食費やレジャー費は全国的に見ても安めで、家計全体のやりくり次第ではローンと暮らしを両立しやすい環境です。
さらに福岡市や県の制度として、子育て世帯や若年層向けの住宅取得支援、リフォーム補助制度も整備されています。これらを活用すれば、返済額の負担を抑えつつ、安心してマイホームを手に入れることができます。
7. ライフプラン全体で考える重要性
住宅ローンは単独の支出ではなく、人生全体の支出の一部です。教育費や老後資金、万が一の医療費や介護費用も同じ財布から出ていきます。ローン返済だけを基準に考えるのではなく、ライフイベントに合わせた長期的なプランニングが欠かせません。特に福岡のように暮らしやすく楽しみも多い地域では、「住宅ローンを払うための生活」ではなく「生活を楽しむための住宅ローン」に位置づけることが、家族にとっての幸せにつながります。
8. 福岡で暮らすからこそ「ゆとりを残す計画」を
福岡は都市機能と自然が近く、暮らしの楽しみが豊富です。天神でショッピングをしたり、博多駅から新幹線で小旅行に出かけたり、糸島や能古島で自然を楽しんだり。住宅ローンに追われる生活では、せっかくの魅力を味わう余裕がなくなります。
「家のために働く」のではなく、「家があるから暮らしを楽しめる」状態を目指しましょう。そのためには、数字だけにとらわれず、自分たち家族の未来の暮らしをイメージしながら返済計画を立てることが大切です。
まとめ
- 毎月の返済額は「借入額」「金利」「返済方式」で決まる
- 元利均等返済は負担が一定、元金均等返済は利息が少なく済む
- 金利0.5%の違いが総返済で数百万円の差に
- フラット35など国の制度を活用すると安心感と優遇が得られる
- 年収500万なら3,000万円前後、年収700万なら4,000万円前後、年収1,000万なら5,000万円前後が現実的
- 教育費は子ども1人で1,000万円超、老後は2,000万円問題といわれる時代。ローンと並行した資金準備が欠かせない
- 「借りられる額」より「暮らしを楽しめる額」で計画を
- 福岡の地域事情や支援制度を活用すれば、より安心した住まいづくりが可能
- 人生全体のライフプランを見据えた住宅ローン選びが、未来の安心につながる
資金調達は、家づくりの中でもとても大切なステップです。
永大ハウスでは、お客様のこれからの暮らしに寄り添いながら、安心して返していける返済額とお借入額を、一緒にじっくり考えてまいります。