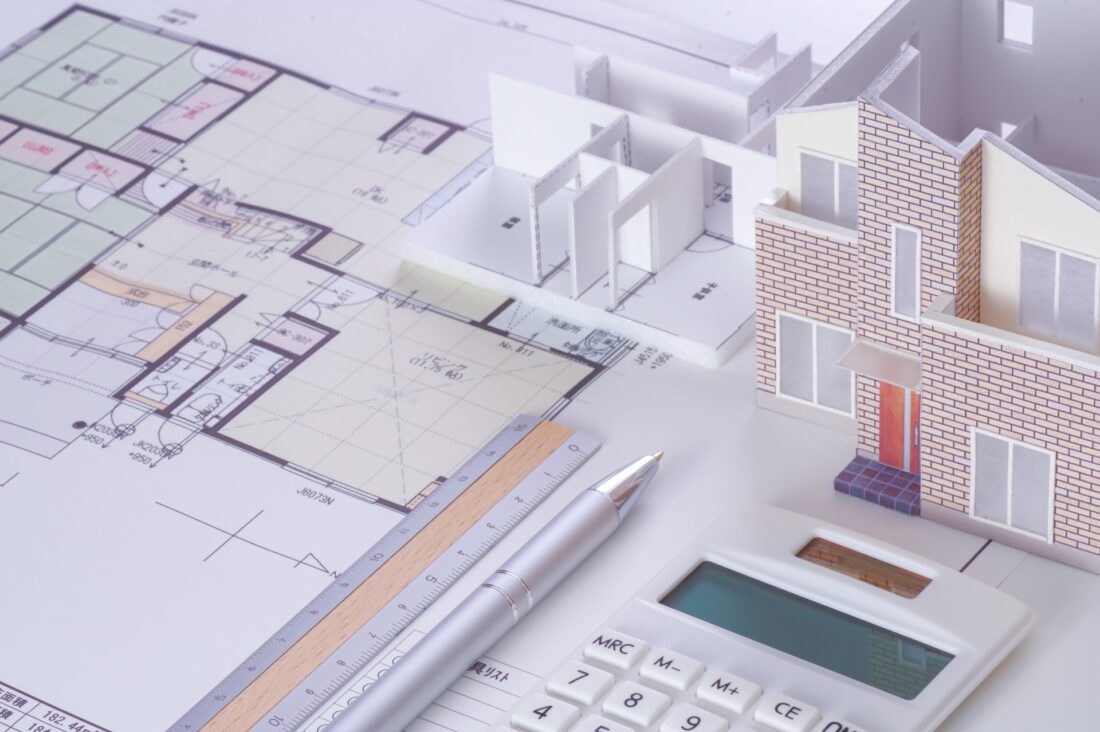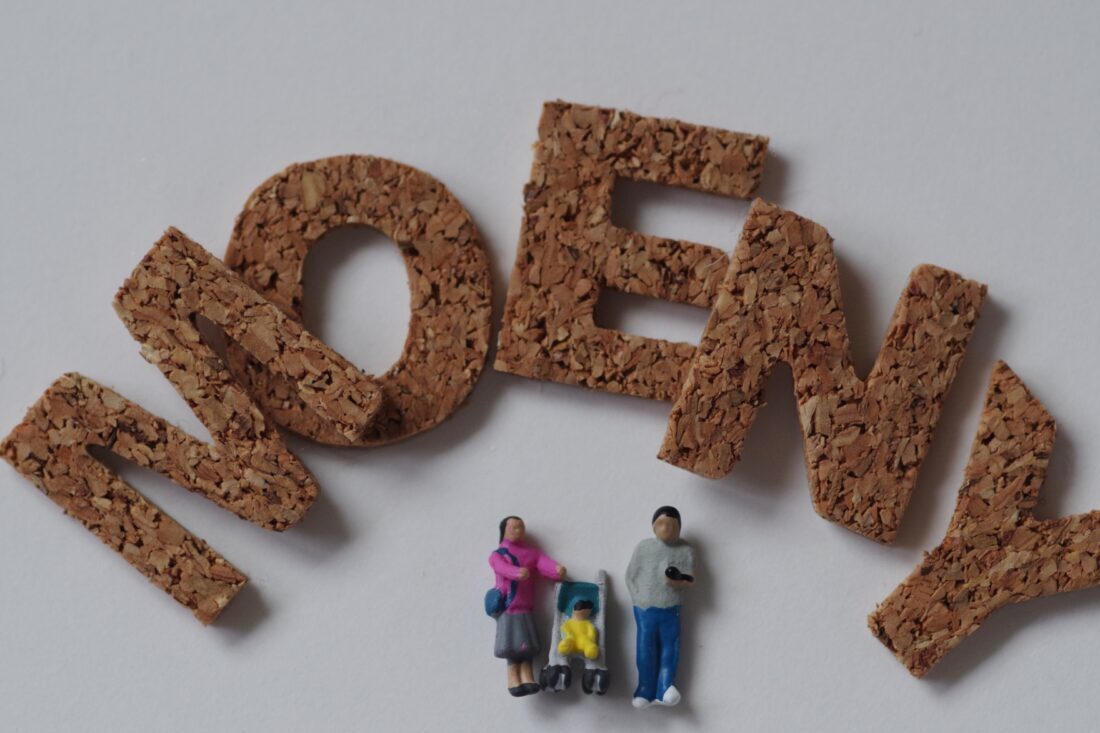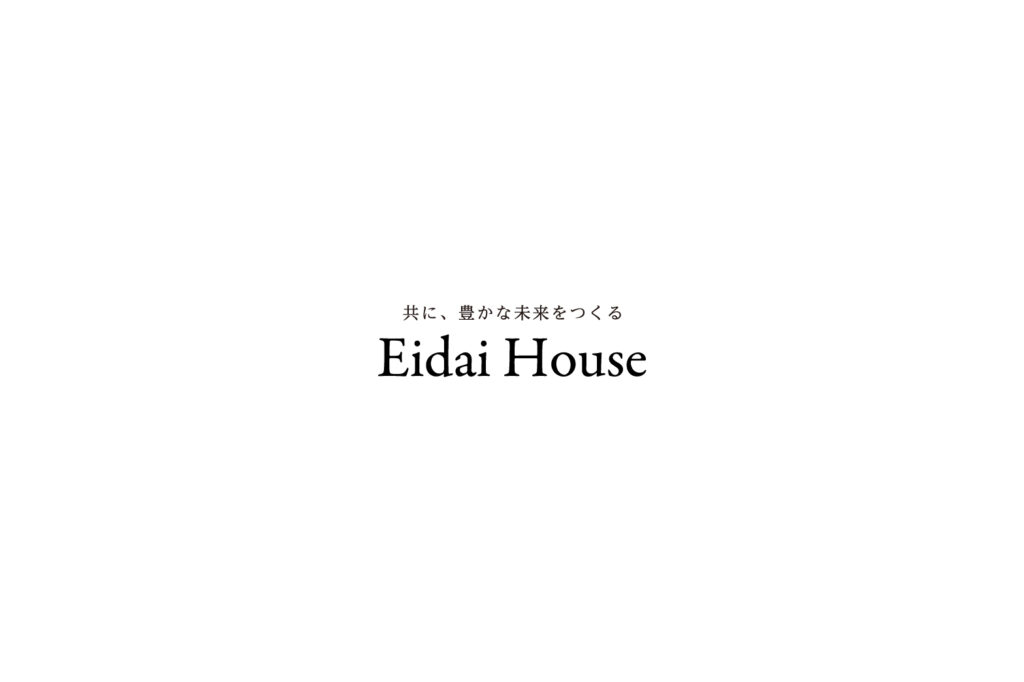目次
はじめに
都市と住宅が近い福岡で、家そのものを「強く、賢く」
福岡市は、中央区・博多区の都心から、早良区・西区・城南区・南区・東区まで、職住学が近接するコンパクトシティです。利便性が高い反面、一戸建ては「窓や出入口が多い」「敷地内に死角が生まれやすい」という弱点を抱えます。本コラムでは、福岡の生活圏を踏まえて、設計(プラン)・外構(エクステリア)・製品(建材)・運用(暮らし方)の4部で、防犯対策を体系化します。キーワードは、①見せる抑止、②時間稼ぎ、③習慣化です。
1章|まず“福岡ローカル情報源”を常時ONにする
最初の一歩は「近所で何が起きているか」を継続的に受け取る仕組みづくりです。福岡県警の「ふっけい安心メール(あんあんネットふくおか)」に家族全員で登録し、通勤通学の動線に合わせて署別配信を設定しましょう。中央区、博多区、早良区、城南区、南区、西区、東区のいずれでも、近隣の不審情報や注意喚起が届けば、照明・施錠・帰宅動線の微調整が即日でできます。併せて自治会・町内会に加入し、通学路の見守りや街頭防犯カメラ設置の議論に参加すると、地域全体の抑止力が底上げされます。
出典:ふっけい安心メール
2章|侵入の“手口”で考える:一戸建ての弱点トップは「無締まり」と「ガラス破り」
全国の傾向では、侵入窃盗の最多は無締まり(施錠忘れ)、次いでガラス破りです。つまり、第一の防犯対策は“当たり前の徹底”。家族全員がドア・窓の施錠状態を習慣として確認すること。勝手口、浴室小窓、2階ベランダの掃き出し窓は見落としやすい要注意ポイントです。ガラス破りは、三角割り・こじ破り・打ち破り・焼き破りなど手口が多様化しています。対策はシンプルで、①鍵に到達しにくくする(補助錠やロック付きクレセントで解錠点を複数化)、②破壊に時間がかかる素材に替える(防犯合わせガラスや面格子、シャッター)という二本柱を同時に行うこと。空き巣が嫌うのは「5分の壁」。突破に5分超を要す家は狙われにくくなります。
参考データや最新の地域情報は、福岡県警の統計コーナーで適宜確認できます。
出典:福岡県警
3章|CPTED(防犯環境設計)を福岡の戸建てに落とし込む

CPTED(セプテッドと読みます)は、①視認性の確保、②領域性の強化、③接近の制御、④対象の強化、という設計思想です。新築計画でもリフォームでも、次の要点をチェックしてください。
・見通し(視認性):植栽は“下見せ・上抜け”を意識し、しゃがんでも身体が隠れにくい形に剪定。高木を窓正面に置かない。駐車場は道路側に人感センサーライトを設け、夜間でも出入口が「ほどよく見られる」状態を維持します。
・領域性:門柱・表札・ポスト・宅配ボックスで境界のメッセージを明確に。「許可のない立入りは目立つ」空気をつくることが抑止になります。アプローチは素材・段差・照明の連続性で動線を誘導し、袋小路に勝手口を作らない。
・接近の制御:足場になる物置・室外機・雨樋の立ち上がりに注意。2階ベランダへ“登れる足場”を置かない。フェンスは乗り越えにくい形状で、視線を遮り過ぎないバランスに。
・対象の強化:窓は防犯合わせガラス+補助錠、勝手口ドアはCPマーク付きに。面格子は外側から外しにくい固定方法を選び、ビス頭露出を避けます。カメラは顔が識別できる2〜3mの距離で玄関を斜めに捉え、駐車場・勝手口・庭もカバー。録画の目的は「抑止+事後特定」です。
4章|“CPマーク”で選ぶ:開口部アップデートの実務
CP(CrimePrevention)マークは、官民合同会議が認める「防犯性能の高い建物部品」の共通標章です。新築では窓・玄関・勝手口をCPで統一、既存住宅では錠前のディンプルキー化+補助錠追加から始め、侵入リスクの高い窓から順に防犯合わせガラス(もしくは厚手の防犯フィルム)へ。チェックポイントは、①ワンドア・ツーロック、②サムターン回し対策(カバー・空回り機構)、③シリンダーの耐ピッキング性能、④採風ドアの格子強度、の4点です。鍵は“借りたまま”にしない運用もセットで。
出典:警視庁 侵入窃盗の防犯対策
5章|「見せる抑止」を設計に組み込む
侵入者は“下見”の段階でハイリスク物件を避けます。よって、抑止を可視化する設計が効きます。具体的には、①「録画中」「センサー作動中」のサインを門柱やアプローチに設置、②ポーチ・勝手口・駐車場に人感ライトを配置して、夜間の影を薄くする、③宅配は宅配ボックスで門前完結——置き配の常態化は不在の可視化につながるため極力避ける、の3点です。旅行時は屋内のランダム点灯タイマーで在宅らしさを演出し、郵便物は一時止めを依頼すると効果的です
6章|日常運用で“情報を漏らさない”
SNSでの位置情報共有は帰宅後に。ジオタグはOFF。鍵は家族内で貸し借りの履歴をメモ化し、不要になった合鍵は速やかに回収。古いシリンダーは早めに交換を。紙類のゴミは氏名・住所が判読できない状態にして破棄し、宅内の生活パターンが外部に読み取られないよう注意します。共働きで昼間不在の場合は、道路側からの視認性と宅配導線の標準化が最優先。玄関と駐車スペースのカメラは、顔・ナンバー・人物の動線が十分に写る画角で固定しましょう。
7章|福岡の地域特性と着眼点(区・エリア別)
・中央区(薬院・平尾・赤坂・鳥飼など)/博多区(住吉・美野島・博多駅南など):人流は多いが、建物裏手の勝手口やサービスヤードが死角になりがち。背面に人感ライト+カメラを。路地の抜けがある街区では、夜間の見通しを意識した外構計画が有効です。
・早良区(西新・百道・田隈ほか)/城南区(別府・七隈ほか):通学路と生活動線が重なるため、子の帰宅時間帯に自動点灯する照明シーンを設定。学童の見守り導線をアプローチに重ねると、領域性と安心感が高まります。
・西区(姪浜・今宿・九大学研都市ほか):新旧の街並みが混在し、カーポートや物置が足場になりやすい。ベランダ到達足場の排除と、駐車スペースの照度確保を最優先に。
・東区(香椎・千早・箱崎・アイランドシティほか):幹線沿いは生活音が多く異音に気づきにくい。窓はCP化し、補助錠で解錠点を複数化。上階でも庇や配管で到達されるため、2階窓も油断しない。
・南区(大橋・長住・若久・野間ほか):商住近接で夜間の人流差が出やすい。勝手口のセンサー照明と録画、裏手の植栽剪定で“隠れにくさ”を維持。音(インターホン応答や犬の存在)も抑止力です。
・近郊(春日市・大野城市・那珂川市・糸島市・志免町・粕屋町など):車移動中心。駐車場からの直侵入を想定して、道路側からの視認性と、門扉〜玄関までの導線照度を確保。宅配ボックスは敷地外から手を伸ばせない位置に固定します。
Q1.新築と既存、どちらを優先すべき?
A.既存は費用対効果の高い順に、①勝手口錠の更新→②主要窓の補助錠→③人感ライト→④危険窓のガラス強化。新築は設計段階でCPTEDを織り込み、窓・ドアはCPで統一するのが最安です
8章|よくある質問(Q&A)
Q2.ペットで人感ライトが誤作動します。
A.検知角と感度を調整できる機種を選び、低照度の常夜灯+人感強発光の二段構成に。低い位置に設置し過ぎないこともポイント。
Q3.在宅ワーク中でも防犯対策は必要?
A.はい。狙いは“人の少ない面”です。表側で在宅でも、裏手の勝手口や庭側が手薄なら狙われます。背面の照明・カメラ・面格子で「裏をやりにくく」してください。
9章|チェックリスト
玄関:ツーロック/サムターン防護/ドアスコープの外し対策。
勝手口:人感ライト/カメラ視界内/足場物の排除
窓:CPガラスまたは防犯フィルム/補助錠/面格子の固定強化/2階ベランダ到達足場の除去。
外構:植栽の剪定/門柱・表札・ポストで境界を明確化/宅配ボックス。
旅行:照明ランダム点灯/郵便一時止め/SNSは帰宅後。
地域:自治会と見守り導線の設計/街頭防犯カメラ導入検討/ふっけい安心メールの登録。
まとめ:最初の一手は「窓」と「勝手口」
福岡市の一戸建て防犯対策は、「地域情報の即時把握」×「CP基準の開口部」×「CPTEDに基づく外構」×「日常運用の習慣化」の掛け算で強くなります。中央区や博多区の都心近接地でも、西区・早良区・城南区・南区・東区、さらに春日市・大野城市・那珂川市・糸島市・志免町・粕屋町といった周辺市町でも、やるべきことは共通です。まずは勝手口と“割られやすい窓”の強化から着手し、照明・カメラ・植栽・宅配導線を点検。家族でルールを共有し、地域と連携して「やりにくい家」「やりにくい街区」を一緒につくっていきましょう。