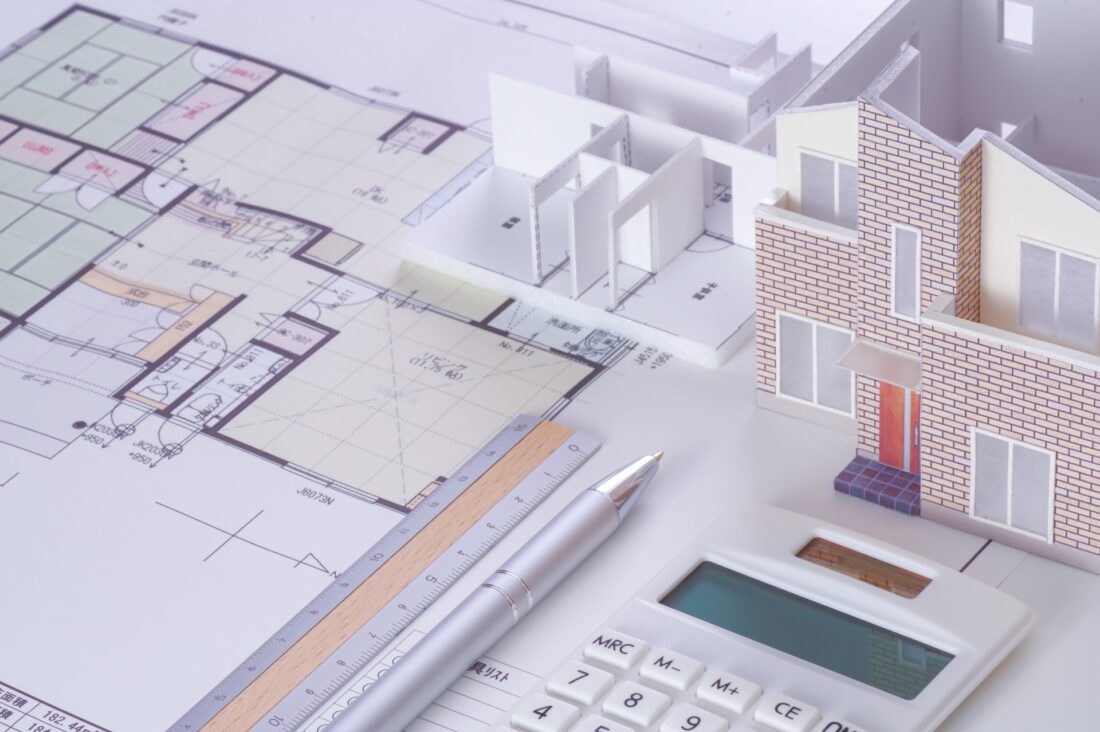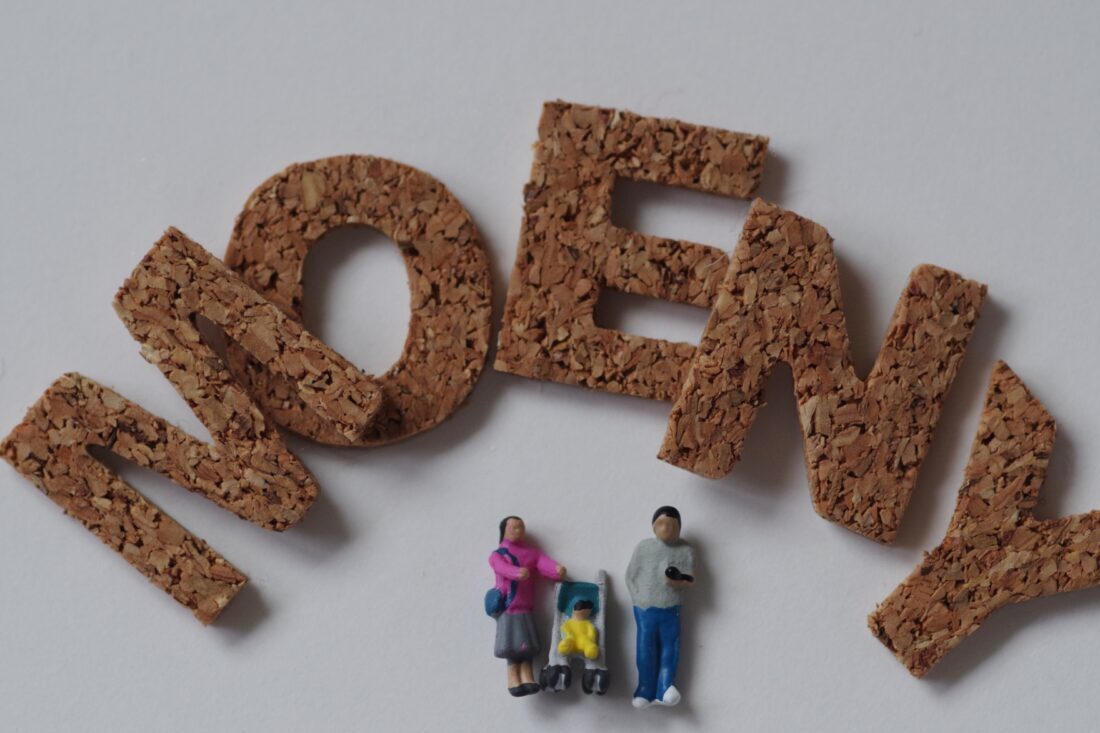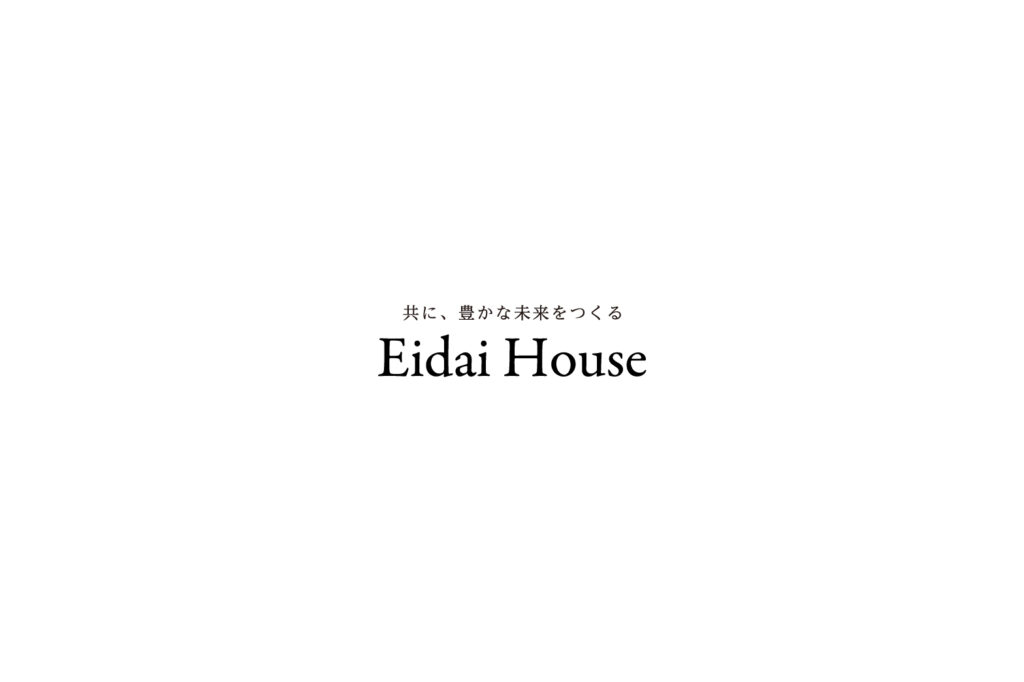目次
はじめに
日本は世界でも有数の地震多発国です。特に、2024年の能登半島地震、2016年の熊本地震、そして2011年の東日本大震災は、各地で甚大な被害をもたらし、私たちに「地震に強い家」の重要性を改めて突きつけました。
福岡市周辺も安全とは言い切れず、近年は活断層の活動や液状化のリスクが注目されています。地震に強い家を建てるには「耐震設計」の理解が不可欠です。
本コラムでは、耐震とは何か、どんな特徴があるのかを詳しく解説し、能登・熊本・福島の地震からの教訓や福岡市の地域リスク、そして耐震住宅の選び方・建て方まで幅広く紹介します。これから注文住宅を検討される方、ご家族の安心を守る家づくりにぜひお役立てください。
第1章:耐震の基本とは?地震に強い家づくりの要点
「耐震」とは、建物が地震の揺れに耐えられる性能のことを指します。耐震住宅は、構造部分の強度やバランスを高め、倒壊や大きな損傷を防ぐことが目的です。
耐震等級とは
耐震性能を示す代表的な指標が「耐震等級」です。建築基準法では最低でも等級1が義務付けられており、等級3が最も高いレベルとなります。
- 耐震等級1:建築基準法の基準を満たすレベル。震度6強から7程度の地震で倒壊・崩壊しない基準。
- 耐震等級2:等級1の1.25倍の耐震性能。消防署や警察署などの公共施設に要求されるレベル。
- 耐震等級3:等級1の1.5倍の耐震性能。災害時の緊急拠点病院などに求められる最高水準。
福岡市での住宅建設でも、この耐震等級の選択が非常に重要です。等級3は長期優良住宅の認定基準にもなっており、安心度が格段に高くなります。
制震・免震の違い
耐震とは別に、揺れを「抑える」技術として制震、免震があります。
- 制震:揺れを吸収・軽減する装置を建物に設置し、揺れのエネルギーを減衰させる方法。
- 免震:建物の基礎と地盤の間に免震装置を置き、揺れを直接伝えないようにする方法。
制震・免震は耐震よりも高度な技術で、主に大型施設や高級住宅で採用されています。福岡市周辺においても、新築注文住宅で取り入れる例が増えています。
第2章:能登半島地震・熊本地震・福島の地震から学ぶ被害の実態
2-1.能登半島地震(2024年1月1日)
令和6年(2024年)1月1日に石川県能登地方を震源として発生したマグニチュード7.6(暫定値)、最大震度7の地震により、241 名の尊い命が失われました。
出展:内閣府 防災情報のページ
地盤の液状化被害も多数報告され、側方流動を伴う大規模な液状化現象が確認されるなど、建物やインフラへの被害は甚大でした 。
2-2.熊本地震(2016年)
熊本地震は連続して震度7の揺れが発生し、多くの住宅被害が出ました。特に木造住宅では耐震等級の低い住宅が倒壊し、基礎の弱さや壁量不足が倒壊原因とされました。
- 被害の特徴:倒壊率が高かったのは築20年以上の住宅が中心。耐震補強されていない古い住宅は大きな損傷。
- 教訓:築年数が経過した住宅は耐震診断と補強が不可欠。耐震等級3の新築は被害が極端に少なかった。
出典:国土交通省 住宅局 木造建築物の倒壊の原因分析(新耐震基準)
2-3.福島地震(2011年 東日本大震災)
東日本大震災は巨大地震と津波を伴い、広範囲で甚大な被害をもたらしました。
- 被害の特徴:津波浸水地域の住宅全壊が多かったが、内陸部でも強い揺れで倒壊した住宅があった。
- 教訓:耐震設計だけでなく立地の安全性確認や高台移転も重要。
第3章:福岡市の地震リスクと防災計画
福岡市の地震リスク
福岡市は活断層が複数存在し、過去にも震度6弱クラスの地震が観測されています。特に市内中心部は液状化のリスクも指摘されています。
- 活断層は福岡市中央区から博多区にかけて存在。
- 液状化危険区域は博多区や東区に多い。
福岡市は防災計画でこれらのリスクを踏まえ、耐震化推進や避難計画の整備を進めています。
出典:福岡市 地域防災計画
福岡県全体の地震状況
福岡県は地震発生回数は比較的少ないものの、南海トラフ巨大地震の影響や内陸の活断層の動きにも注意が必要です。
- 九州北部は断層活動が活発な地域もあるため、油断は禁物です。
- 福岡県は住宅の耐震基準を満たす新築率が高いものの、築古物件の耐震補強は進行中。
出典:NHK 福岡NEWS WEB https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20250331/5010027585.html
第4章:耐震等級・制震・免震の違いと最新技術

耐震等級の詳細
建築基準法は等級1を最低基準と定めていますが、多くの専門家は等級3を推奨します。理由は、地震の際の安全性はもちろん、保険料の割引や住宅ローン減税の優遇にもつながるからです。
- 耐震等級3の住宅は倒壊リスクが最も低く、長期的な安心を約束します。
- 国土交通省も等級3を取得する住宅建築を促す傾向にあります。
制震・免震技術の進歩
近年は耐震に加えて制震装置を導入する住宅も増えています。例えば、建物の柱や梁にダンパーを取り付け、揺れのエネルギーを吸収します。
免震住宅は基礎部分に免震ゴムを敷くことで揺れを大幅に軽減し、家具の転倒や家屋の損傷を最小限にします。
福岡市内の新築高級住宅では、これらの技術の導入も徐々に進んでいます。
コスト面にも反映しますので、ご自身にとって必要かどうかは、住宅メーカーにご相談されることをお勧めいたします。
第5章:地震に強い住宅設計と構造のポイント
建物のバランスと壁量計算
耐震設計で重要なのは「壁の量と配置」です。バランス良く壁を配置し、地震力を分散させることで建物の揺れを抑えます。
- 壁量不足は、倒壊の最大の原因。
- 福岡市の設計事務所では、最新の耐震診断ソフトを使い詳細な計算を実施。
基礎構造の強化
基礎がしっかりしていないと、いくら壁が強くても意味がありません。地盤調査を徹底し、適切な基礎形状や補強を施します。
- 地盤の液状化対策も重要。深い基礎や地盤改良工事で対応。
木造・鉄筋コンクリート造の耐震性
福岡市で多い木造住宅は、適切な構造用合板や金物補強がポイントです。RC造(鉄筋コンクリート造)では、耐震壁やダンパーの設置が効果的。
第6章:築年数別の耐震診断・補強リフォーム事例
築20年以上の住宅の耐震診断
熊本地震の教訓も踏まえ、築20年以上の住宅は耐震診断を受けることが推奨されています。
- 福岡市では自治体や専門業者が耐震診断を支援。
- 診断の結果に応じて、壁の増設や基礎補強を行うリフォームが増加中。
具体的な補強工事の例
- 筋交いの追加設置
- 金物補強の増設(ホールダウン金物など)
- 基礎のひび割れ補修と鉄筋増設
第7章:ご家庭の防災意識と日常の備え

耐震住宅を建てることは大切ですが、家族の防災意識や備えも欠かせません。
避難経路・避難場所の確認
地震や風水害など、いつ災害が起きてもおかしくない現代において、自分の命を守るための行動を事前に知っておくことは非常に重要です。
福岡市では区ごとに避難所が指定されており、日頃から確認しておくことが重要です。
防災グッズの準備
水や食料、懐中電灯、携帯充電器など、最低3日分の備蓄を推奨。
地震や災害時に、ライフラインが止まっても自力で生き延びるために、水や食料、懐中電灯、携帯充電器などの備えは欠かせません。最低3日分と言われますが、大規模災害では1週間分が推奨されることもあります。
家具の固定
地震による家具の転倒は大怪我の原因。壁面への家具固定を習慣づけましょう。
家具の固定を習慣づけることは、家族の命を守るための最も効果的な対策の一つです。特別な技術は必要ありません。今すぐできる対策を一つずつ実行に移し、安心して暮らせる家づくりを始めましょう。
第8章:まとめ:福岡市で安心できる家を建てるために
福岡市における「耐震」は、単なる構造強化だけではありません。地域の地震リスクの理解、最新技術の採用、そしてご家庭の防災意識の向上が組み合わさって初めて実現します。
- 熊本・能登・福島の震災から得た教訓を忘れず、築年数や立地に応じた対策を。
- 耐震等級3の取得や制震技術の導入で、より安全な住まいを。
- 福岡市の各区の防災情報を活用し、日頃から備えることも不可欠。
永代ハウスでは、お客様一人ひとりのご要望や土地条件に合わせ、最適な耐震設計と安心の家づくりを提案しております。ご相談はいつでもお気軽にお声がけください。